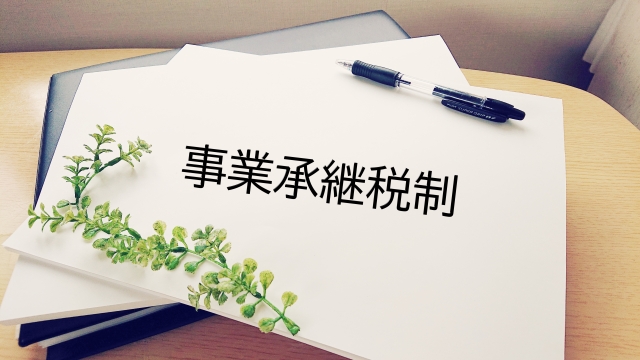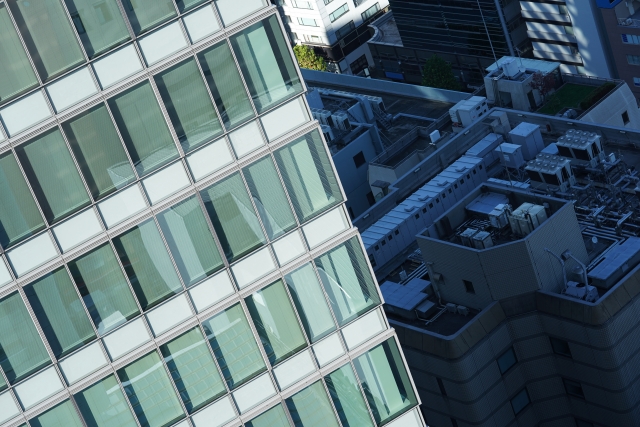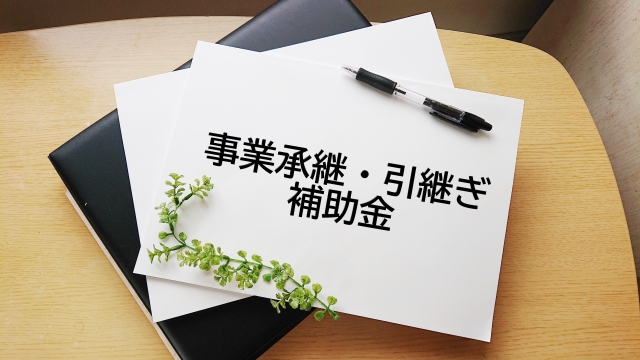帝国データバンクが公表したレポート「M&A に対する企業の意識調査」(TDB Business View 2025/01/28)によれば、「今後 5 年以内に『M&A に関わる可能性がある』企業は 29.2%となり、前回調査(2019 年6月調査)に比べて 6.7 ポイント低下した。一方で、今後 5 年以内に『M&A に関わる可能性はない』企業は、規模、業界のいずれの項目でも前回調査を上回り、M&A に対する警戒感が高まる結果となった。」とされています。
M&Aが一種のブームのようになっている中、昨年は、買い手側の不適切な M&A が問題化するほかM&A仲介業者のコンプライアンスの問題も顕在化しています。業界全体でも自主努力を進めていますが、途半ばというところでしょうか。
かっては、”乗っ取り”的なイメージもあり、あまりいい印象はなかったM&Aですが、現在では、事業承継の重要な手段になっていることには、間違いはありません。
令和 6 年度における事業承継・引継ぎ支援センターの実績
独立行政法人中小企業基盤整備機構(理事長:宮川正 本部:東京都港区)が、5月30日に全国の事業承継・引継ぎ支援センターにおける令和 6 年度の実績を公表しています(令和 6 年度 事業承継・引継ぎ支援センターの実績について「第三者承継(M&A)の成約件数が過去最高を更新」(中小機構 News Release))。
このNews Releaseによれば、「令和 6 年度の相談者数は 23,000 者を超え、事業承継・引継ぎ支援センター開設以来の累計相談者数は 15 万者超となりました。特に、第三者承継(M&A)に関する相談が伸びており、第三者承継に関する相談者数は 16,045 者、累計では約 12 万者となりました。これを受けて、令和 6 年度の第三者承継の成約件数は 2,132 件と過去最高を更新しました。」としています。
また、「第三者承継のうち、創業希望者と後継者不在の中小企業・小規模事業者とのマッチングを行う後継者人材バンク)の成約件数も、106 件と過去最高となりました。後継者人材バンクへの新規登録者(創業希望者)数は 1,551 者で、累計登録者数は 1 万者を超えました」としています。
昨年は、M&Aにおける「買い手」側の不適切な行為という問題が顕在化し、併せてM&A仲介業者のコンプライアンスの問題も取り沙汰されました。このようなことを背景にしてか、帝国データバンクの調査結果(TDB Buiness View、2025/1/28発表) によれば、「近い将来(今後 5 年以内)においてM&A に関わる可能性はない」は 50.5%となり、規模、業界のいずれの項目でも前回調査を上回った。企業からは、M&A 仲介業者の買い手・売り手に対する公平性や悪質な買い手による M&A の動向に疑念を抱く声が多数寄せられた。とりわけ、小規模企業など売り手側の M&A に対する警戒感が高まっている。」とされています。
なお、このようなことから、M&A業界の自主努力も進んではいますが、M&A に対する法規制強化の必要性について望む考えが多いようです。
経営者の高齢化・健康リスクと事業承継の準備不足(遅れ)の問題
帝国データバンクが発表した「後継者難倒産の動向調査(2024年度)」(TDB Buiness View、2025/04/07発表)によると、後継者不在による倒産は依然として高水準で推移しており、企業経営における深刻な課題となっています。とりわけ、経営者の高齢化が進む中、病気や死亡といった不測の事態が増加し、事業継続が困難になるケースが増えているというこよです。
同記事によると、「後継者難で倒産した企業を倒産時の社長平均年齢を算出すると、2024年時点で69.8歳に及び、過去10年でみても70歳前後で推移している」という現状です。
また、同じく帝国データバンクが発表した「『経営者の病気、死亡』倒産動向調査」(TDB Buiness View、2025/04/07発表)によると、「2024年の「経営者の病気、死亡」を主因とする倒産は316件で、前年比38件(13.7%)増加し、初めて300件を超えました。」、「全倒産に占める割合も年々上昇し、かつては1%台にとどまっていたものが、2013年に2%台となり、ここ2年は3%台に達しています。」という現状です。
同記事では、「50歳以上の社長の割合は2017年の77.2%から2023年には81.0%に増加し、経営者の高齢化が進行」、一方、「社長交代率は3.8%と低水準で推移」としています。
このように、経営者の病気、死亡のリスクが高くなる高齢化に対応した新陳代謝が進んでいない状況です。同記事では、さらに、「70代の社長で28.5%、80代以上で23.2%が後継者不在」「事業承継の計画中止・取りやめる割合は、社長年齢が高くなるにつれて上昇」としています。
なるほど、確かに、加齢とともに、気力・体力が落ち、M&Aを含めた事業承継への取組み、新たな販路開拓・取引先拡大、新商品・新サービスを開発、異業種への参入など新たな取組みに後ろ向き、あきらめ感が強くなるのは、人間として、自然とも言える状態だと思います。
しかし、中小企業庁が今年5月に公表した「中小M&A市場の改革に向けた方向性について(2025年5月9日 中小企業庁)」(以下「公表資料」)によると、「休廃業・解散数は増加傾向にあり、特に2024年は前年比で大きく増加。事業承継ではなく退出した者も相当程度存在することが示唆される。このうち、黒字で休廃業・解散をした者の割合は引き続き50%以上となっている。」(P10)としています。
この”事業承継ではなく退出した者”の中には、前記のあきらめ感により退出された方も多数いらっしゃるかと思います。また、公表資料では、「経営者年齢の分布の変化をみると、一定程度事業承継が進展していることが示唆されるものの、未だ事業承継が必要となる70代の事業者が多く存在。加えて、今後承継が必要本格的に必要となる60代の層も多く存在している。」(P7)「中小企業・小規模事業者数は、経営者の年齢が60歳代の事業者が最も多く、79万者存在。 また、経営者の年齢が70歳以上の事業者数は98.6万者であり、事業承継が必要な層が多く存在。」(P24)とし、特に、地方圏にて顕著としています。
黒字でありながら、休業・廃業を選択するのは、雇用の確保、地方地域経済の活性化の観点からも、いわゆる勿体ない状態です。今後の業界・事業の成長性や財務状況等により、全ての中小企業が第三者承継の実現可能性があるかは、確定的ではありません。一定程度の取捨選択は必要かと思いますが、ポテンシャルのある中小企業については、M&Aによる第三者承継で事業を継続する意義はあるかと思います。
今後の対策、あり方
鍵は、まず、経営者が考え、知ることが第一歩
前記の「中小M&A市場の改革に向けた方向性について(2025年5月9日 中小企業庁)」では、中小企業の事業承継問題解決の糸口となる”事業承継・M&A”の浸透について、あらゆる角度から検討、その方向性を示しており、とても参考になる資料です。
しかし、このような公表資料を今後の事業継続についてどうすべきか悩んでいる高齢経営者の方々がご存じでしょうか。
最近では、物価高、原材料費・燃料費等の高騰、人件費の高騰、円安、関税の問題など目先の経営・事業運営に目一杯で、とても事業承継まで考えが及ばないという方々も多いと思います。
また、前記のとおり、M&A に対する警戒感、不信感から思考を停止させてしまうなどの障壁もあるかと思います。
なので、今後のご自身の会社又は従業員を含めた会社の企業価値とも言える事業をどうしたいのか、まず、考えることから始めるのがきっかけになるのだと思います。そして、考えるためには、情報が必要です。私もあと9ケ月で満60歳となりますが、60代、70代の方々は、やはり、中小企業の事業承継や中小M&A等に関する最新の知識に触れる機会が中々ないかもしれません。また、いきなり、M&A仲介会社等に相談するのもハードルが高いかもしれません。もし、身近にそのような相談が出来るとしたら、取引先金融機関の行員でしょうか。
そのような意味で、思考を始めるために、最終的に民間のM&A仲介会社等に話しを持って行くにしても、まずは、ご自身の頭の中である程度、具体的なスキームやプラン、展望等を描くために、公的機関等に相談するのも一つの方策だと思います。
現在は、以下のように、各種の支援機関の設置及び支援策が講じられています。事業承継をするには何をやればいいか?悩んでいる方は、一度、ざっくばらんでもいいので、相談されてもよろしいかと思います。
〇事業承継の支援策(中小企業庁HP)
〇事業承継・M&Aに関する主な支援策(2024年6月 中小企業庁)
後継者難対策のポイント(最初に最後を思う)
以上を踏まえ、既に、各所又は書籍等で示されていますが、後継者難対策のポイントですが、概ね、以下のとおりです。
1. 早期の事業承継計画の策定と準備
事業承継には5〜10年の準備期間が必要とされており、早期に計画を立てることが重要です。これにより、経営者の高齢化や健康リスクを軽減できるかと思います。
2. 親族内・親族外承継の検討
親族内承継が難しい場合、親族外承継(従業員や外部人材への承継、外部招聘、MBO)を検討することも一つの方法です。
3. M&Aの活用
前述のとおりです。
4. 専門家や支援機関への相談
この節では、4番目となっていますが、まずは、相談だと思います。
なお、前節の続きになりますが、事業承継の前に、まずは、自社の事業を自分の代限りとし、将来的に廃業するか、または、事業承継のスキームは兎も角、事業の継続をしたいのか、早めの段階で大まかにでもいいので方向性を決めておくことが肝要かと思います。事業の将来性、世の中の流れ、従業員の生活など色々な角度から早めの段階で想定し、情報を収集し、準備をしておく。
国も円滑な廃業や廃業後の生活をサポートする仕組みも各種講じています(例えば、相談窓口として、中小企業庁が各都道府県に設置している「よろず支援拠点」」など)。やはり、早めの決断が、後継者難対策の最も有効な対策かと思料します。
(参考)バリエーションの問題(企業価値、株主価値、のれんなど)
前述したとおり、全ての中小企業に第三者承継の実現可能性があるわけではありません。事業承継にあたっては、一般的には親族内承継も含めて、いわゆる事業の磨き上げを行い、事業価値を高めるとことが大事と言われています。
しかし、これだと少し、抽象的なので、M&Aの実現可能性のスタート地点に立つために何がポイントという点について、企業価値、株主価値、そして、「のれん」という概念を中心に、記述したいと思います。
M&Aの成否は、買い手の場合、クロージング後の事業統合(PMI)の成否まで見ないとわかりません。一方、M&Aによる事業承継を行う側(売り手)から見た場合のM&Aの成否の判断は、いくらで売却できたか、自分の納得のいく売却価格だったかということに尽きるかと思います。しかし、その前に、そのスタート地点にまず立たないといけません。
そのためには、M&Aにおける買取(売却)価格がどのような基準で算定されるのかを知っておくことは、とても大事だと思います。すべての算定方法については、私もまだ不勉強で、また、多種多様なので、この記事で全てを書くことは出来ませんが、代表的なものについて触れたいと思います。
取引所の相場がある上場企業と違い、中小企業の株式は客観的な評価をすることは難しいと言われています。評価方法にも様々な方式があり、売手の所属する業種・業態等によってM&Aの成約率や譲渡対価には違いがあり、売買当事者間の関係によって、妥当な評価方式も違ってくる場合もあります。
会社の値段がいくらか、何を基準に算定するのかという基本的な考え方、概念は、言葉で表すと、会社の「事業価値(又は事業資産などの経済的価値)」に非事業資産を加えた「企業価値(EV=Enterprise Value)」から「有利子負債相当額」を差し引いた「株主価値」が株式買取り額(=M&Aによる売買価格)になると言われています。
実際には、企業価値(事業価値)の評価額は一物一価ではなく、様々な評価方式がありますが、代表的なものとして、「コストアプローチ(資産価値からの評価」「マーケットアプローチ(比準方式)」「インカムアプローチ(収益還元方式)」の3つがあげられます。この記事ではこれら評価方式の詳細な説明はしませんが、3つのアプローチは一長一短があるため、実務上は、併用したり組み合わせたりして価格が算定されているようです。
特に、M&Aにおける価格算定は、DCF方式(Discount Cash Flow method、インカムアプローチの一種)が主流になってきているようですが、未上場の中小企業におけるM&Aでは、前記の「コストアプローチ」の一種である「時価純資産額」による評価を価格とする方法が実務的な対応となっているようです。
この「時価純資産額」の定義は色々な表現があるのですが、資産から負債を差し引いた簿価純資産に資産の含み益を加算し、そこから、資産の含み損及び簿外の負債を控除した「時価純資産」(簿外の資産を加算する方法もあり)を価格とする算出方法です。
また、ケースによっては、この「時価純資産」に営業利益の3年から5年分を加算するして方法もあるようです。
さらに、「時価純資産額」にいわゆる「のれん」の分を加算する方法もあるようです。「のれん」とは、特許などの知的財産権や商権、ブランド、知名度、信用力、技術力など目に見えない経済的価値と指すと言われています。
この「のれん」ですが、適切に評価が出来れば、現在の価値である「時価純資産額」に将来の価値を反映させることができますが、理論的なのれんの計算方法は確立されていないようで、実務的に、「のれん」のみを評価(算出)するのではなく、前記の「DCF方式により算出された価格」と「時価純資産額」との差額が「のれん」として認識されているようです。
「のれん」という言葉ですが、”老舗である”、”大手メーカーの下請け”とか”優秀な人材がいる”とか抽象的なイメージが先行し易いかもしれませんが、M&Aにおいては、このような通念とは違い、その会社又は事業の買収後に期待できる”収益力”そのものを指しています。したがって、収益を生まないブランドや商権は、前記の企業価値を形成しないため、端的に言うと、意味がありません。「M&Aにおける買収価格算定において、まずつかまえるべきは、対象会社が本業からどれくらいのキャッシュを生み出す力を持っているかだ。」(「バリエーションの教科書」(森生 明著、東洋経済新報社)P62)でもあるように、買収側は対象会社の資産価値に対する超過収益力がどれくらいあるかということが、M&A実行にあたっての大事な判断基準になると思われます。
このような観点から、第三者承継(M&A)において、財務状態が健全であるという前提(若干、傷んでいる場合も含む。)で、営業利益でも「のれん」でも、将来的な超過収益力がどれくらいになるかということを、客観的、合理的に証明(算定)できるかがが、第三者承継の実現可能性のスタート地点に立てるひとつの条件だと思います。特に、「のれん」について、それが明らかになれば、一つのアドバンテージになるかと思います。
そして、事業の磨き上げは、「のれん」の磨き上げが最優先課題事項になるかと思料します。
なお、この「のれん」の会計処理については、定期的に償却する日本基準を見直し、IFRS(国際会計基準)や米国基準に準じた定期償却しない(ただし、厳しい減損処理あり)方法に変えようとする動きがあります。
このため、首相の諮問機関である規制改革会議が5月下旬に、のれんの会計処理について「非償却」または「非償却か償却の選択制」に変えることを答申で提起し、企業会計基準委員会(ASBJ)に検討を要請しました。
今後のM&Aの動向を考えるうえで、気になる点です。
※当ブログで掲載している内容は、個別の事案に対するアドバイスや具体的な判断を示すものではなく、一般的な情報や解説を目的としています。記載内容は、公表資料及び書籍等から当ブログ運営者が情報収集し、情報提供を目的として、現時点での一般的な概要を参考としてまとめたものになっています。よって、記載内容は、あくまでも、当ブログ運営者の認識や理解に基づくものであり、実際の法律や会計上の判断・手続きについては、必ず専門家(弁護士・税理士・公認会計士等)や公的機関にご相談いただき、自己責任においてご判断くださいますよう、お願いいたします。当ブログは、掲載内容に基づくいかなる損害や損失に対しても責任を負いません。