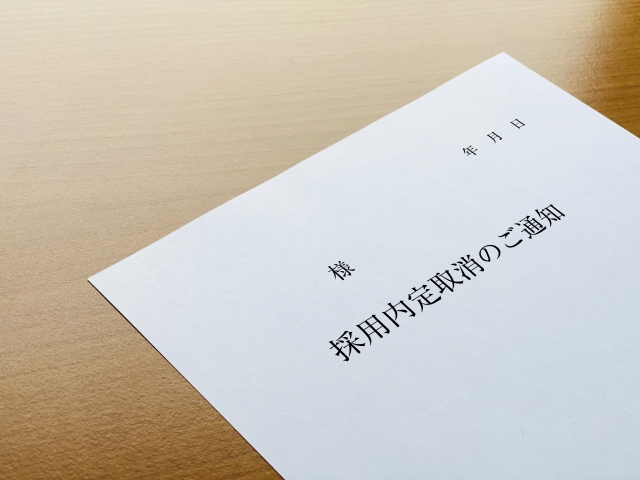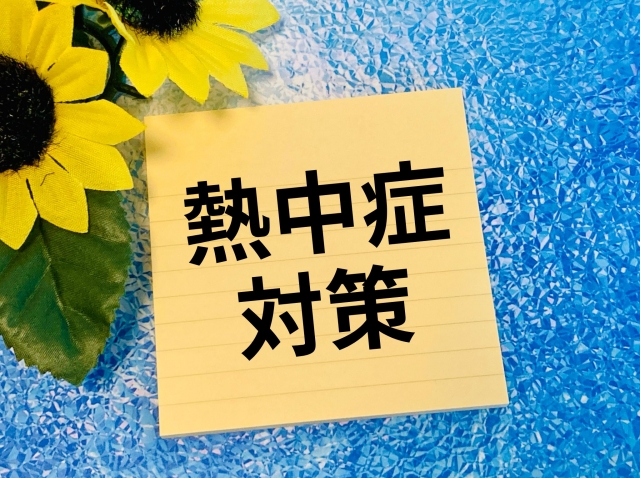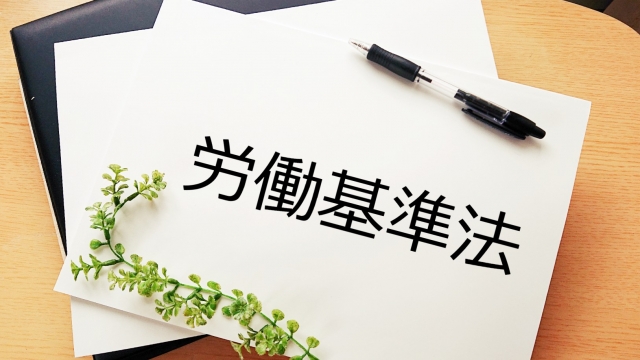先日、特定社会保険労務士でもあるにもかかわらず、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)」(以下、「派遣法」)についての基本的な知識が欠落しているのが判明しました。自省と復習を兼ね、この記事を書かせてもらいます。
なお、この記事では、労務DDにおいて調査する対象会社が派遣先である場合について、記述します。
労務DDにおいて調査する主な事項
主な調査事項の概要
派遣先における労務DDを行うにあたって、その中心となる調査項目は、大要、次の三つになるかと思います。
①派遣先の講ずべき措置について遵守状況の確認
②違法派遣に該当する事由がないかの確認
③二重派遣に該当する事由があるかの確認
派遣先の講ずべき遵守状況とは
たとえば、次の①から⑦のようなものがあります(「M&Aにおける労働法務DDのポイント〔第2版〕東京弁護士会労働法制特別委員会 企業集団/再編と労働法部会【編著】」P132)。
①派遣先責任者の選任(派遣法第41条)
②派遣先管理台帳の作成(派遣法第42条)
③離職後1年以内の労働者の受入れ禁止(派遣法第40条の9)
④特定有期雇用派遣労働者の雇用安定措置(派遣法第40条の4)
⑤労働者募集に関する事項の周知(派遣法第40条の5)
⑥比較対象労働者の待遇情報の提供(派遣法第26条第7項、第10項)
⑦派遣料金について、派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式による待遇改善が行われるよう配慮(派遣法第26条第11項)
これらの遵守事項のうち、①及び②に違反した場合は、30万円以下の罰金(刑事罰)を受ける可能性があります。
違法派遣とは
違法派遣とは、次の①から⑤をいいます(「M&Aにおける労働法務DDのポイント〔第2版〕東京弁護士会労働法制特別委員会 企業集団/再編と労働法部会【編著】」P132)。
①労働者派遣事業の禁止業務の提供を受け従事させた場合(派遣法4条)
②無許可事業主からの労働者派遣の役務を受けた場合(派遣法第24条の2)
③事業所単位の期間制限(原則3年)に違反して派遣労働者を受け入れた場合(派遣法第40条の2第1項)
④個人単位の期間制限(3年)に違反して派遣労働者を受け入れた場合(派遣法第40条の3)
⑤いわゆる偽装請負の場合(派遣法第40条の6第1項第5号)
違法派遣を受入れた派遣先は、労働契約申込みみなし制度(派遣法第40条の6)の適用があり、派遣先は違法派遣受入れ時点で、派遣先は派遣労働者に対して派遣就業に係る労働条件と同一の労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされ、派遣労働者が派遣先に直接雇用を求めれば、みなし申込み対する承諾の意思表示となり、労働契約が成立してしまい、予定外の人員を雇用しなければいけなくなるリスクが生じる可能性があります。このことは、M&A統合後のPMIに少なからず影響が生じる可能性があると思います。
また、これらに違法派遣を受入れた場合、派遣法違反として、行政指導・助言(派遣法第48条第1項)、改善命令(同法第49条第1項)、勧告(同法第49条の2第1項)及び勧告に従わない場合の企業名公表(同条第2項)の対象となり得ます。これは、対象会社を買収する側のレピュテーション(reputation)リスクを生じさせる可能性があります。
なお、派遣先が①~⑤にあたることを知らず(善意)、かつ知らなかったことに過失がなかった(無過失)ときは、労働契約申し込みみなし制度は適用されません。
二重派遣とは
二重派遣とは、派遣会社(派遣元)から派遣された労働者を受け入れた派遣先企業が、その労働者をさらに別の企業(再派遣先)に派遣し、実際に再派遣先の指揮命令下で業務に従事させる行為をいいます。派遣法は、派遣元が雇用責任を負う場合に限り派遣を認めているところ、二重派遣は、派遣先が、再派遣に当たり、雇用責任を負わないから、再派遣は派遣には該当せず、職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下「職安法」)第44条が禁止する労働者供給事業となります。この場合、二重派遣に関与した派遣元と派遣先は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(職安法第64条第10号)、また、労働基準法第6条違反(中間搾取の禁止)として、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(労働基準法第118条第1項)を受ける可能性があります。
なお、この刑罰については、両罰規定(行為者だけではなく、法人も罰せられる)になっています(労働基準法第121条、職安法第67条)。さらに、レピュテーション(reputation)リスクを生じさせる可能性があります。
事業所単位の期間制限(原則3年)・個人単位の期間制限(3年)について
意外と盲点になっていると思われる期間制限(3年ルール)の運用
前記まで記した調査項目である違法派遣及び二重派遣のうち、労働者派遣事業の禁止業務の提供を受け従事させた場合、無許可事業主からの労働者派遣の役務を受けた場、偽装請負の場合、二重派遣の場合などイリーガル的な要素が強いものについては、通常の企業であれば、これらに該当するケースは、そう多くはないと思います。
問題というか、意外と盲点になっているのが、いわゆる「3年ルール」だと思います。
事業所単位の期間制限(原則3年)・個人単位の期間制限(3年)とは(概要)
平成27年の労働者派遣法改正により、派遣社員の「同一事業所・同一配置」での派遣可能期間が原則3年に制限される、別途「3年ルール」が導入されました。
この3年ルールは、派遣先の事業所単位の期間制限と派遣労働者の個人単位の期間制限の二つがあります。
【事業所単位の期間制限】
定義:同じ派遣先の「事業所」(例:工場、店舗、支店など)で、派遣労働者(誰でも)の受け入れができる期間は「原則3年まで」に制限されます。
カウント方法:その事業所に最初の派遣労働者を受け入れた日から3年です。途中で派遣社員が入れられても、カウントはリセットされません。
例)2022年4月1日にAさんが察しました→2025年3月31日が事業所単位の「3年ルールの満了日」(この翌日である2025年4月1日が「抵触日」)。
延長の条件:派遣可能期間終了の1ケ月前までに過半数労働組合や労働者代表の意見聴取を行い、必要な手続きを踏めば、「3年ごとに何度でも延長」ができます。
ポイント1:クーリング期間を空けた場合を除き、派遣労働者を受け入れた以降3年までの間に派遣労働者が交替したり、他の派遣会社と労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。(クーリング期間:派遣期間終了後3ケ月を超える期間。この期間を超えると派遣可能期間(3年)は、リセットされる。)
ポイント2:事業所単位の派遣期間制限違反の派遣受け入れの場合には、当該事業所で受け入れている派遣労働者の全員が労働契約の申込みの対象となってしまいます。
【個人単位の期間制限】
定義:派遣労働者「個人」が、同じ「組織単位」(課や配置など)で働けるのは「とりあえず3年まで」に制限されます。
カウント方法:派遣社員ごとに、その配置・課ごとで3年間が上限。業務内容や派遣会社が変わっても、3年という期間制限は、仮に派遣元が変更された場合でも通算されます。
延長不可:個人単位の3年制限は延長できません。3年を超えて同じ配置で働くことはできません。
ポイント:事業所単位の期間制限を延長した場合でも、同一の組織単位で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。
| 規制単位 | 対象 | 期間制限 | 延長の可否 |
|---|---|---|---|
| 事業所単位 | 派遣先の事業所に取り組む全ての派遣労働者 | 同じ事業所で通算3年 | 過半数組合等の意見聴取で可 |
| 個人単位 | 派遣労働者個人と同じ組織単位(課・配置など) | 同じ組織単位で通算3年 | 原則不可 |
3年ルールの例外
3年ルールには例外があり、以下の①から⑤に該当する場合は3年ルールは適用されず、同じ派遣先の同一の事業所・同一の部署で3年経過後も継続して受け入れが可能となります。なお、本記事では、各項目の詳細な説明は省略させていただきます。
① 派遣元で無期雇用契約を結んでいる派遣労働者(派遣法第40条の2第1項第1号)
② 60歳以上の派遣労働者(派遣法第40条の2第1項第2号)
③ 有期プロジェクトに従事する派遣労働者(派遣法第40条の2第1項第3号イ)
④ 日数が限定されている業務に従事する派遣労働者(派遣法第40条の2第1項第3号ロ)
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の代替として従事する派遣労働者(派遣法第40条の2第1項第4号第5号)
盲点になっている事業所単位と個人単位の関係
まず、簡単にいうと、どちらの制限も、早く派遣期間が満了した日が優先されます。しかし、実際は事業所単位の期間制限の方が優先されます。そのため、事業所単位での派遣派遣労働者は個人単位の派遣期間制限が残っていたとしても、事業所単位の期間制限を超えて働くことはできません。
例えば、A派遣会社から派遣されたBさん、派遣期間満了(抵触日)は3年後になりますが、Bさんが派遣されてきてから2年後にC派遣会社からDさんという人が派遣されてきました。Bさんは、「事業所単位」及び「個人単位」でも3年で派遣期間満了となりますが、残されたDさんはこの時点でまだ抵触日まで2年間あるから、その後の引き続き働けるかというと、そうではありません。A派遣会社に係る「事業所単位」の派遣期間制限のため、A社及びBさんの抵触日以降働くことは、派遣法違反となります(このため、「事業所単位」の期間制限を延長するため、過半数労働組合等の意見聴取と記録の保存を行います。)。
「個人単位」の期間制限(3年間)だけに目が向きがちで、前記の【事業所単位の期間制限】のポイントで記したとおり、「クーリング期間を空けた場合を除き、それ以降3年までの間に派遣労働者が交替したり、他の派遣会社と労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。」ので、もしかしたら、いつのまにか、期間制限を超過している可能性があり、この場合、派遣法労違反となり、労働契約申込みみなし制度の適用がされ、当該事業所で受け入れている派遣労働者の全員が労働契約の申込みの対象となってしまうことから、予期せぬ採用を強いられ、また、その後処理に忙殺される可能性があるかもしれません。
このことから、事業所単位の期間制限を超えていないか、超えている場合、過半数労働組合等(代表者の選出の適法性の確認も含む)への意見聴取に係る記録等について確認が必要で、仮に、期間延長の手続きが不備であった場合、その旨と該当する派遣職員の人数等をDD報告書において報告することになると思います。
※労働法務DD以外の観点からは、派遣社員を受け入れている事業所は、今一度、一番最初に派遣を受け入れた年月日から時系列に整理し、クーリング期間の有無を確認のうえ、「抵触日」の確認を行い、そのうえで、各個別の派遣労働者の抵触日がいつになるかを重ね、前記のように「事業所単位」の抵触日の制限により、派遣可能期間が短縮されるものがいなかなどを確認して、過半数労働組合等からの意見聴取をいつまで行わなければいけないかの計画を策定すべきと思います。
このように、派遣の期間制限は「事業所」と「個人」の2つの単位があり、それぞれに3年間の上限が設けられています。延長できる場合やできない場合、また起算日やリセットの条件など複雑な点も多いため、適用を誤らないよう注意が必要です。
閑話休題(派遣先の雇用安定措置と無期雇用派遣労働者)
最近、身近で、”ある派遣会社(派遣元)から派遣先に派遣されている無期雇用派遣労働者について、派遣元担当者から、派遣先に当該無期雇用派遣労働者を正職員として雇用してもらいたいとの話があった”ということを聞きました。話しを聞くと、その派遣先は小規模の事業所でとても正職員を登用する余裕はないのですが、そのような事情にも関わらず、派遣先に今後の正職員の採用予定も聞かず、また、紹介予定派遣の申し込みでもなく、唐突にそのような話があったそうです。さらに、聞くと、派遣元担当者はその派遣労働者が”無期雇用派遣労働者だから派遣期間の制限がない”(=どうやら、このまま更新し続けるなら正社員として採用してくださいという趣旨だと思います)ことを前提にして、話しをしてきたそうです。
3年ルールが導入された際、多くの派遣会社は、無期雇用派遣労働者を採用したようです。無期雇用派遣労働者は、正社員ですから、派遣先(就労先)が見つからない場合でも給料等を支給しなければいけません。派遣業のビジネスモデルは、派遣社員が働いて得た報酬の一部を手数料として得ること(職安法で禁止されていう労働者供給事業の例外)です。派遣職員は、文字通り、人財で、私が派遣会社の社長なら優秀な派遣社員がいれば、手放しません。
派遣元担当者がどのような意図で、正社員登用の話しをしてきたかわかりません(もしかしたら、その無期雇用派遣労働者が派遣元に派遣先にお願いするよう、頼んだかもしれません。この場合、いわゆる転職ですね。)。また、話をすること自体は問題はありませんが、無期雇用派遣労働者だからといって派遣先が無期限に更新するとは限りません。そのようなことに、こじ付けて、そのような話をしてきたとしたら、「何をかいわんかや」です。
派遣法第40条の4では、派遣先が講じる雇用安定措置義務として、特定有期雇用派遣労働者の雇入れ努力義務が規定されています。詳細な説明は省略しますが、前記にあがった無期雇用派遣労働者は、この特定有期雇用派遣労働者には該当しません。なぜなら、派遣元で無期に雇用されているから、雇用が安定しているからです。
常用代替の防止という観点からは、正社員への登用等の検討、措置等は必要かつ大事なことだと思いますが、たとえ、その派遣職員のたっての希望だったにせよ、その小規模という実情や事業所の性格も踏まえ、派遣先の人事に関する事情や実際の職員採用の予定等を事前に確認することをせず(事前調整なしに)ストレートに派遣先に打診してくるやり方には、少し、違和感を感じました。
また、誤解を恐れずにもう少し敢えて踏み込んで言わせてもらうと、仮に、正職員を採用するとしたなら、そのような小規模事業所であるとはいえ、選考基準(知識、知能、経験、能力、コミニュケーション能力その他の求める選考水準)は、自ずとハードルが高くなると思います。そして、その無期雇用派遣労働者がその求める選考水準をクリアしているかについては、派遣期間が長期になると見込まれるということとは、別の問題です。その辺りに考えが及ばず、ただ本人の希望のみをもって、正職員への採用を要請してくるのは、事業所の専有の人事権を軽く見ていていると言っては、大袈裟でしょうか。
無論、派遣元にもその無期雇用派遣労働者との関係ほか諸事情もあるでしょうし、その打診がどのくらいのトーンだったのか(もしかしたら、軽く言ったに過ぎないかもしれません。)、私も実際には聞いていないので、断定的にものを言うことはできませんが、もう少し、丁寧な、段階を踏んだ仕事の仕方もあってよさそうです。
※当ブログで掲載している内容は、個別の事案に対するアドバイスや具体的な判断を示すものではなく、一般的な情報や解説を目的としています。記載内容は、公表資料及び書籍等から当ブログ運営者が情報収集し、情報提供を目的として、現時点での一般的な概要を参考としてまとめたものになっています。よって、記載内容は、あくまでも、当ブログ運営者の認識や理解に基づくものであり、実際の運用等は、必ず専門家(弁護士・社会保険労務士、コンサルタント等)や公的機関(厚生労働省等)にご相談いただき、自己責任においてご判断くださいますよう、お願いいたします。当ブログは、掲載内容に基づくいかなる損害や損失に対しても責任を負いません。