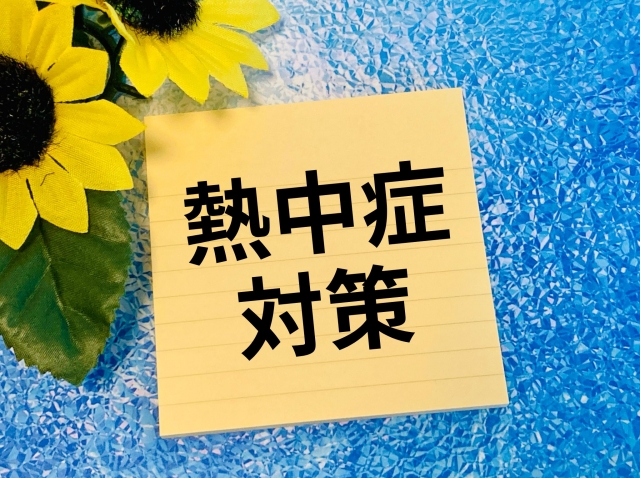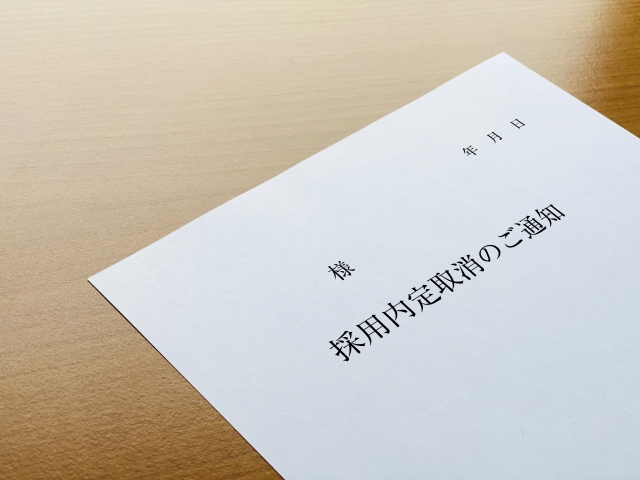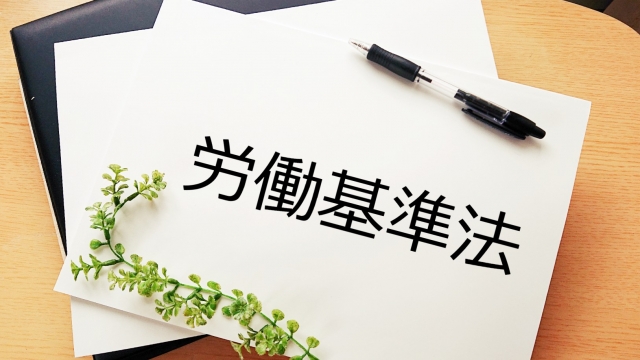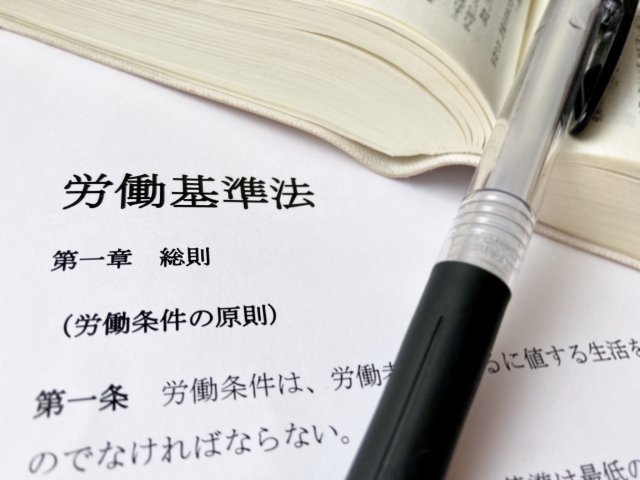私は都内在住ですが、ここ2、3日は、台風の影響もあってか(?)、暑さが少し和らいだ感がありますが、その前は、6月から猛暑、酷暑が続き、夏本番を迎える今後のことを考えると、気持ちがしんどくなります。
さて、厚生労働省は5月30 日、令和6年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況を発表しました。職場の熱中症による死傷者数(死亡及び休業4日以上)は1,257 人と前年から151 人、14%増加し、統計を取り始めた2005年以降最多ということです。また、死亡者数は31人で、3年連続で30 人以上。業種別に死傷者数を見ると、製造業235 人、建設業228 人、運送業186 人の順で続いており、約4割が製造業と建設業で発生しています。
このようなこと背景にして、それと私の勝手な予測ですが、これから先・毎年、益々、暑くなっていく、もはやかっての日本ではない気象現象(酷暑)が恒常的に続くことも予想されることから、厚生労働省は、すべての事業者に熱中症対策を義務付けた労働安全衛生規則(昭和47年9月30日 労働省令第32号、以下「安衛則」)の一部を改正する省令を令和7年6月1日に施行、同月20日に「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(基発0520第6号 令和7年5月20日)」(以下「施行通達」を発出しています。
今回の記事はこの内容を簡単にご紹介したいと思います。
熱中症対策の概要(安衛則の一部改正)
安衛則とは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)という法律と労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)という政令に基いて制定された命令(厚生労働省令)です。法律と政令の委任条項を受けて法律・政令に書かれた労働災害の防止のための危害防止基準や責任体制等の詳細な事項を定めているものです。
さて、今回の安衛則の一部改正ですが、冒頭に記したように、熱中症対策です。
義務付けの内容
概要
安衛則の一部改正では、暑熱な場所において連続して行われる作業など熱中症を生ずるおそれのある作業を行うとき、①熱中症の自覚症状を有する作業者、または、熱中症が生じた疑いのある作業者を発見した者がその旨を報告する体制整備をあらかじめ整備すること(例:事業場における緊急連絡網 、緊急搬送先の連絡先及び所在地等)、②作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察、処置を受けさせることその他の実施に関する手順をあらかじめ定めること、③作業を従事する者に、あらかじめ、①及び②を周知させることを事業者に義務付けしています。
「暑熱な場所」とは
施行通達によれば、熱中症を「『熱中症』とは、高温多湿な環境下において、体内の水分や塩分(ナトリウム等)バランスが崩れる、体温の調整機能が破綻する等して、発症する障害の総称であること。」と定義し、「『暑熱な場所』とは、湿球黒球温度(WBGT)が28度以上又は気温が31度以上の場所をいい、必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨であること。」としています。
また、「『暑熱のある場所』に該当するか否かは、原則として作業が行われる場所で湿球黒球温度又は気温を実測することにより判断する必要があるが、例えば、通風のよい屋外作業について、天気予報(スマートフォン等のアプリケーションによるものを含む。)、環境省の運営する熱中症予防情報サイト等の活用によって判断可能な場合には、これらを用いても差し支えないこと。」とされています。
なお、WBGTとは、「Wet-Bulb Globe Temperature」の略で、「湿球黒球温度(単位:℃))の値は、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数」とされています(施行通達(別紙)「職場における熱中症予防基本対策要綱」P1)。
そして、これを測定するのが、WBGT測定計ですが、言葉だとピンと来ないので、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課のパンフレット「WBGT値を把握して熱中症を予防しましょう」にこの測定計の画像が掲載されているので、リンクを貼っておきます。
WBGTは、「Wet-Bulb Globe Temperature」の略で、「湿球黒球温度(単位:℃))の値は、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数」とされています(施行通達(別紙)「職場における熱中症予防基本対策要綱」P1)。
そして、これを測定するのが、WBGT測定計ですが、言葉だとピンと来ないので、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課のパンフレット「WBGT値を把握して熱中症を予防しましょう」にこの測定計の画像が掲載されているので、リンクを貼っておきます。
(備考)「WBGT値を把握して熱中症を予防しましょう」では、作業者の身体状況別(作業内容やその強度別)又は順化(作業環境に適するように体質が変化する状況、要は、暑熱に適応しているか)別のWBGT基準値に加え、着衣の組み合わせにより基準値に加えるべき補正値も掲載されています。単純にWBGT値だけを見るのではなく、作業環境、作業条件、着衣条件により基準値が変わってくるということです。
「暑熱な場所において連続して行われる作業など熱中症を生ずるおそれのある作業」とは
施行通達によれば、「『暑熱な場所』において、継続して1時間以上または4時間を超えて作業が行われることが見込まれる作業」とされています。
「周知」とは
施行通達によれば、「『周知』は、報告先等が作業者に確実に伝わることが必要である。その方法には、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によることがあり、原則いずれでも差し支えないが、伝達内容が複雑である場合など口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行うこと。」とされています。
また、「現場で周知した結果の記録の保存までは法令では求めていないが、労働基準監督署による確認に際しては、事業者として適切に対応することが求められること。」とされているので、留意する必要があると思います。
罰則
施行通達によれば、今回の安衛則の一部改正による新設された安衛則第612条の2は、労働安全衛生法第22条に基づくものとしています。よって、今回改正で事業主の措置義務として課された熱中症対策違反については、労働安全衛生法第22条違反となり、同条に基づき、「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。
熱中症対策措置義務の対象事業者
熱中症対策というと、建設現場、運送業務、警備現場、農作業など屋外作業場や高温多湿な環境な作業場の製造業等のいわゆる「現場」のイメージが強いですが、今回の改正は、労働安全衛生法第22条に基づくものであり、措置義務の対象は、労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者(=事業を行う者で、労働者を使用するもの)で、全事業者が対象となることが要留意です。
この点については、施行通達でも「改正により新設される労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第612条の2は、労働安全衛生法(注略)第22条に基づくものであり、個々の事業者に対し、措置義務が課されるものであること。」としています。
なお、熱中症による死傷者数発生割合が高い製造業と建設業のうち、請負構造が複雑な建設業に関連して「建設現場にみられるような混在作業であって、同一の作業場で複数の事業者が作業を行う場合は、当該作業場に関わる元方事業者及び関係請負人の事業者のいずれにも措置義務が生ずるものであること。この場合の作業者に対する周知の方法として、各事業者が共同して1つの緊急連絡先を定め、これを作業者の見やすい場所に掲示することや、メールでの送付、文書の配布等が考えられること。なお、上記のような複数事業者が混在して作業を行う状況において当該措置が行われていなかった場合には、元方事業者のみに違反が生ずる訳ではなく、当該作業場に関わる全ての事業者に同条違反が生ずるものであること。」(マーカーは、筆者が追記)としているように、各事業者ごとに熱中症対策を講じる必要があります。
労災と労災民訴への影響
今回の改正は、罰則付きということが一つ注目された点ですが、ここでは、今回の改正(新設)に伴う労働者災害補償保険法による労災認定と主には事業主側の安全配慮義務違反による労災民訴への影響について簡単ではありますが、触れたいと思います。
まず、いわゆる労災への影響ですが、既に、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第一の二又は同規則これに基づく厚生労働大臣告示で構成される「職業リスト」により、「暑熱な場所における業務による熱中症」が労災補償の対象疾病範囲に含まれているので、業務起因性(業務と災害との因果関係の有無)等の条件が揃えば、業務災害として労災認定される可能性はあります。なので、今回の改正による影響はないと思います。
次に、いわゆる労災民訴ですが、何か大きく変わることはないと思いますが、一つ、事業者側の安全配慮義務違反の立証責任(事業主は十分な熱中対策等を講じていなかった事実を証明する責任)は、被災者側(損害賠償を請求する側)にありますが、改正前は何をもって、対策不十分か明確な基準がなかったですが、今回の改正により、事業主側が最低限講じなければいけないものがはっきりしたので、争う側からすると、立証責任のハードルは下がったかもしれません。
なお、最近では、労災認定の際に使用者側から提出された資料につき、情報開示請求がなされ、労災民訴の証拠として利用される例もままあるそうです(この証拠は必ずしも労災民訴を審理する裁判所を拘束しません。)。また、今回の熱中症対策は罰則付きなので、労働基準監督署の捜査、刑事事件として立件され、検察庁への送致、起訴となり刑事事件となった場合、条件付きですが、事件記録の閲覧,コピーができるようです(最高裁判所ホームページより)。
このようなこともあることから、被災者側の立証責任は、し易くなったのではないかと思います。
最後に
厚生労働省の資料によれば、熱中症による死亡災害の傾向として、そのほとんどが、「初期症状の放置・対応の遅れ」によるものだそうです。近年の日本国内の暑さは、温暖化等による影響もあるのでしょうか、かっての夏の気候とは全く違うものと肌で感じます。このため、四季の移り変わりが豊かで、独自の文化を生んだ日本の良き光景、歳時模様が最近消えつつあり、二季になっていると感じます。
街を歩いていると、ビルの解体た道路舗装工事で働く人々・警備員の方々、最近の人手不足でこれらの業務に従事する方は比較的に体力がない高齢者の方が多いと感じます。これらの方々が倒れてしまったら、最悪の場合、その業務を停止せざるを得ない状況になるかもしれません。最近では、人手不足による倒産件数も増加傾向にあります。このような観点からも、各事業者の方々には、今回の措置義務だけに留まらず、それを上回る十分な熱中症対策を講じることについて、積極的に検討を進めるべきかと思料します。なお、人の命の重さも考えながら。
(参考)「職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)」
(参考)「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)」(厚生労働省 富山労働局)
※当ブログで掲載している内容は、個別の事案に対するアドバイスや具体的な判断を示すものではなく、一般的な情報や解説を目的としています。記載内容は、公表資料及び書籍等から当ブログ運営者が情報収集し、情報提供を目的として、現時点での一般的な概要を参考としてまとめたものになっています。よって、記載内容は、あくまでも、当ブログ運営者の認識や理解に基づくものであり、実際の運用等は、必ず専門家(弁護士・社会保険労務士、コンサルタント等)や公的機関(厚生労働省等)にご相談いただき、自己責任においてご判断くださいますよう、お願いいたします。当ブログは、掲載内容に基づくいかなる損害や損失に対しても責任を負いません。