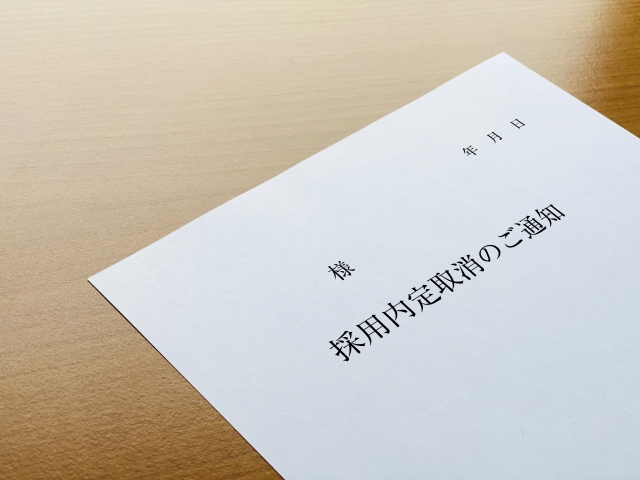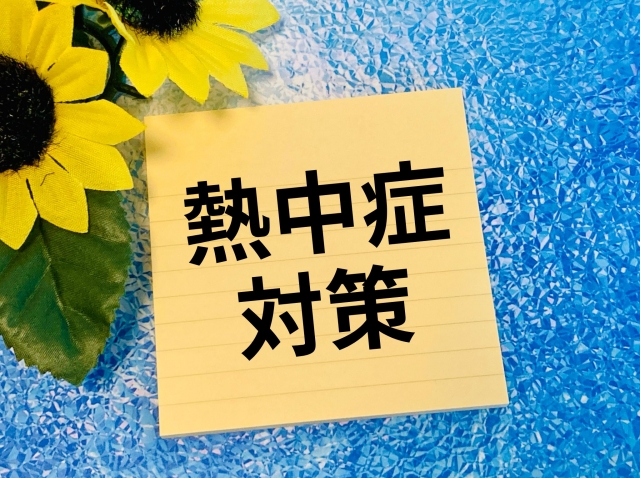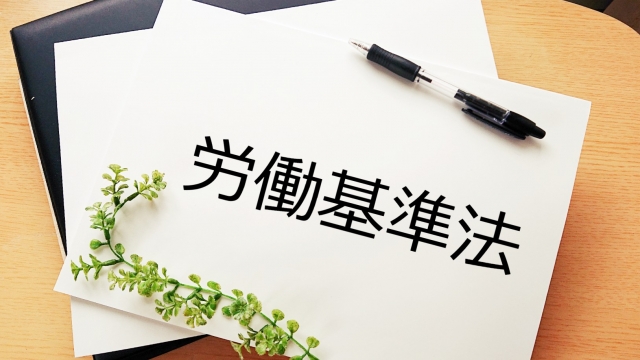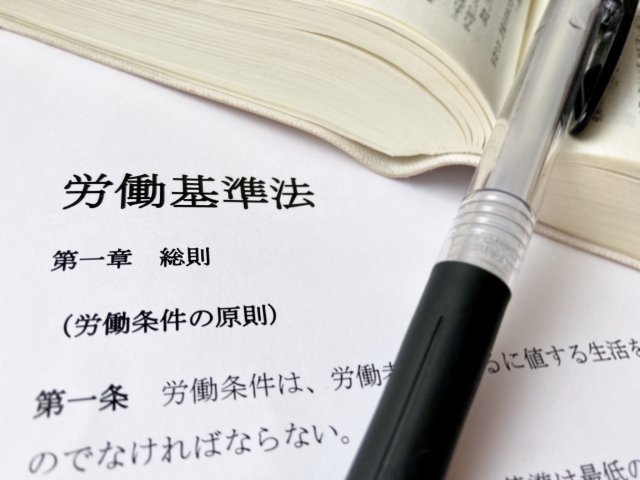今回の事件において、亡くなられた方に対してご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様にお悔やみ申し上げます。奥様やお子さんのことを大事に思いつつも、それでもなお、自殺という選択肢を選ばざるを得なかった男性(当時38歳)の無念、心の怒りを感じます。また、ご自身もまだ38歳であり、これからの人生の展望や抱負もあったかと思います。
※本記事の情報源は、新聞記事等のみとなっています。筆者の方で、事案に関する資料を見たり、事案に関する正確な事実関係を全て把握しているわけではありません。したがって、ブログ記事の内容は、事案の内容又は当事者等に対して具体的に言及するものではありません。新聞記事等の記載内容による事案(事件)を一般化したうえで、筆者の考えを書かせてもらっています。予めご了承ください。
事案の概要
亡くなった男性は、2019年からセブンイレブン本部とフランチャイズ(以下「FC」)契約を結んだ大分県内の加盟店で店長として勤務。店長として、従業員の採用や勤務シフトの作成、商品の陳列から発注までを担い、2022年7月に自殺されたということです(朝日新聞、令和7年4月7日朝刊1面、2面。以下、同。)
遺族(妻)が約1年4ケ月間に及ぶ連続勤務による過労で精神障害を発病したと労災申請を行った。所轄する労基署(労働基準監督署長)は、自殺する前日に亡くなった男性が重度のうつ病を発症したこと認定、発病前の6ケ月間の連続勤務と当該うつ病との因果関係(業務起因性)を認め、2024年11月に労災認定がされていたということです(業務災害の認定の詳細については、筆者の過去の記事「カスハラに起因する自殺の労災認定」をご覧ください。)。
亡くなった男性の妻によると、結婚した2021年3月以降の約1年4ケ月間はほぼ休みがなく、就業規則には「休日は少なくとも週1回」とされていましたが、いわゆる36協定で休日労働させられる日数を「月5日」としていたため(同)、連続勤務を強いられる状況が続いた模様です。
新聞記事(同)によると、時系列的は定かではありませんが、遺族側がセブンイレブン本部側の労務管理上の責任を問うたところ、以下のような回答があったそうです。
〇故人は店舗オーナーと雇用契約を締結しており、労働基準法などの法令を遵守(記事では「順守」。筆者にて修正)する義務はオーナーが全面的に負う。セブン本部は負わない。
〇従業員の勤務状況を本部が個別にチェックするのは物理的・客観的に不可能だ。
また、労災認定後の朝日側の取材に応じての回答と思われますが、セブン&アイ・ホールディングス広報が、以下のようなコメントをしているとのことです(同)。
〇フランチャイズの個店に関わる内容で、本部として答える立場にない。
〇店舗運営は加盟店と本部の明確な役割分担に基づく。
〇採用・教育・労務管理などの「人のマネジメント」は加盟店の役割
なお、朝日の記事が出た7日に、セブンイレブン本部は「事案を受け、加盟店における労務管理のサポートを強化する」とのコメントを発表しています。同社の広報によれば、今後、勤怠管理システムの改善など連続勤務の防止策を検討するとのことです。また、セブンイレブン本部は「従業員の労務管理は契約上、加盟店の役割だが、フランチャイズ本部としても非常に重要であると認識している」等ともコメントしています。
日本にけるフランチャイズビジネスの現状とコンビニ業界の状況
日本におけるフランチャイズビジネスの現状
現在、わが国において、フランチャイズ契約は非常に多様な業種で活用されており、コンビニ以外にも多岐にわたるビジネスで見られます。直営店や一部のみFCの場合もあるようですが、業種・業態の例を大まかにあげると、以下のとおりです。
〇飲食業(ファストフード、カフェ、ラーメン店、うどん・そばチェーン、居酒屋、スイーツ・デザート店、ベーカリー、テイクアウト・デリバリー専門)
〇小売業(ドラッグストア、100円ショップ、書店、リユースショップ、家電販売、クリーニング店、自転車販売)
〇サービス業(美容室・理容室、整体・マッサージ・リラクゼーション、学習塾・教育、英会話教室、保育・託児所、家事代行・清掃サービス、コインランドリー運営)
〇フィトネス・健康関連(フィットネスジム、ヨガスタジオ、パーソナルジム、鍼灸・整骨院)
〇自動車関連(ガソリンスタンド、カー用品販売・整備、コインパーキング運営、洗車・車検専門店)
〇宿泊・観光(ビジネスホテル、ゲストハウス・簡易宿泊、カラオケボックス、ネットカフェ)
〇IT・通信・その他(携帯ショップ、パソコン教室、無人販売、写真スタジオ、不動産仲介)
〇ペット関連(トリミングサロン、ペットホテル・しつけ教室、ペット用品販)
〇物流・配達(宅配便取次弁当・給食宅配)
〇飲食業(ファストフード、カフェ、ラーメン店、うどん・そばチェーン、居酒屋、スイーツ・デザート店、ベーカリー、テイクアウト・デリバリー専門)
〇小売業(ドラッグストア、100円ショップ、書店、リユースショップ、家電販売、クリーニング店、自転車販売)
〇サービス業(美容室・理容室、整体・マッサージ・リラクゼーション、学習塾・教育、英会話教室、保育・託児所、家事代行・清掃サービス、コインランドリー運営)
〇フィトネス・健康関連(フィットネスジム、ヨガスタジオ、パーソナルジム、鍼灸・整骨院)
〇自動車関連(ガソリンスタンド、カー用品販売・整備、コインパーキング運営、洗車・車検専門店)
〇宿泊・観光(ビジネスホテル、ゲストハウス・簡易宿泊、カラオケボックス、ネットカフェ)
〇IT・通信・その他(携帯ショップ、パソコン教室、無人販売、写真スタジオ、不動産仲介)
〇ペット関連(トリミングサロン、ペットホテル・しつけ教室、ペット用品販)
〇物流・配達(宅配便取次弁当・給食宅配)
以上のとおり、数値での証左ではありませんが、業種や業態を見る限り、私たちの日常生活から娯楽など生活の隅々まで、FC契約に基づくサービス等の提供が行われているのがおわかりになるかと思います。このように、フランチャイズはあらゆる分野に広がっており、「スケールが可能で再現性が高いビジネスモデル」(=誰が運営しても、同じように成功しやすい仕組みが整っているビジネスモデル)であれば、ほぼすべての業種で展開可能で、日本経済の中に浸透していると言っても過言ではありません。
FCでは、資金力もなく、無名であっても、さほど経験がない場合でも、親企業(本部・フランチャイザー)とのFC契約により、親会社(本部)の商号・照合やブランドを使用でき、独立した事業者(社)としてオーナー(経営者)になれる一方、親会社(本部)の方は、① 自己資金を使わずに店舗拡大できる、② 固定費がかからない運営が可能、③安定した収益(ロイヤリティ)が得られる、④ブランド力が全国・地域に拡散する、⑤地域密着型の柔軟な運営ができる、⑥従業員の労務問題やトラブルの大部分は、加盟店側が直接対応するため、親会社(本部)の法的・労務的リスクが軽減されるなどのメリットがあり、成功を目指す加盟店オーナーと事業展開を図る親会社(本部)ほ、ある意味、win-winの関係にあると言えます。
FCコンビニにおける過重労働・連続勤務と過労死
コンビニ業界では長時間労働が常態化しているケースが多く、特にフランチャイズ加盟店のオーナーや従業員に負担が集中する傾向があるとのことです。直接な要因は、「24時間営業・年中無休」のため、人手が足りないとシフトを回すために経営者自身や限られた従業員が連日勤務することが多くなるためと言われています。また、近年においては、慢性的な人手不足もあり、さらに、拍車を掛けている状況になっていると思われます。
FCコンビニ加盟店との雇用契約関係にある労働者の労働関係法規の適用と裁判例
基本的な考え方
まだ裁判例の集積はありませんが、過去には、コンビニ加盟店主(オーナー)と親会社(本部)との関係で、コンビニ加盟店主の労働基準法上の「労働者性」を争った事案(セブン-イレブン・ジャパン事件:東京地判平成30年11月21日労判1204号83頁)では、コンビニ加盟店主(オーナー)は独立の事業者として経営していたものであって、労働者であることと本質的に相容れない等を論拠としてその「労働者性」を否定されています。
また、コンビニエンスストアーのフランチャイジーである店長らにより組織された団体からのフランチャイザー(本部)への団体交渉申し入れについて、一部の都道府県の労働委員会において、加盟店主(オーナー)の就労の実態に即して労働組合法上の「労働者性」を判断した事案もあります。
しかし、セブン‐イレブン・ジャパン事件(中労委平31年3月15日労経速2377号3頁等)では、顕著な事業者性を有するなどととして「労働者性」を否定し、国・中労委(セブン‐イレブン・ジャパン事件:東京地判令和4年6月6日労判1271号5頁)及び国・中労委(セブン‐イレブン・ジャパン事件:東京高判令和4年12月21日労判1283号5頁)も、その判断を支持しました。
本事案は、加盟店主(オーナー)と雇用関係にある従業員との法律関係が問題となりましたが、上記の事案と同様に、親会社(本部)とFCコンビニ加盟店従業員との法律関係、すなわち、労働基準法における規定の保護を受けるには「労働基準法上の労働者」に該当する必要があります。
また、労働契約に関する民法の特別法である労働契約法上の適用(保護)を受けるためには、「労働契約法上の労働者」に該当する必要があります。同じく、前記の労働組合法の適用(保護)を受けるには、「労働組合法上の労働者」に該当する必要があります(「労働契約法上の労働者性」の判断については、「労働基準法上の労働者の判断と同様の考え方」とされています(厚生労働省通達「労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号)」)。
これを踏まえると、第一義的には、FCコンビニ加盟店従業員は、加盟店主(オーナー)と雇用契約を結んでいるので、FCコンビニ加盟店の労働者が連続勤務、長時間労働したこと等により精神障害が起きた本事案は、加盟店内の労務問題と言えることが出来ると思います。
ファミリーマート過労死事件(和田事件)
少し、古い事件になりますが、コンビニ大手・ファミリーマートのフランチャイズ(FC)加盟店で働いていた男性従業員(当時62歳)が死亡したのは、長時間労働によるものだとして、遺族が同社と加盟店主(オーナー)に損害賠償を提訴しました。2016年、大阪地裁で和解し、同社が連帯して和解金4300万円を支払うことになった事案があります。
この男性は、2011年から大阪府大東市の店舗で勤務。2012年からは別の店舗でも勤務していました。2012年12月に、脚立から転落して頭の骨を折り、急性硬膜下血腫で翌月(2013年)に死亡しました。労災認定は、仕事中に発生した事故であったことから、問題なく認定されましたが、遺族は、過労による転落だとして提訴しました(いわゆる「労災民訴」)。死亡前の半年間の残業時間は、月218〜254時間にのぼると主張。裁判では、同社の使用者責任を問うていました。コンビニのフランチャイズ本部が解決金の支払いに応じたのは異例のケースだったといわれています。
現行の労働基準法上での解釈の限界とFCコンビニ加盟店従業員の保護、霖雨蒼生
和田事件における法的主張
雇用契約関係に入った従業員(労働者)の生命、身体等の必要な安全配慮(保護)については、労働契約法第5条により「使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うこと」が規定されています。労働契約法制定前においても、判例において、労働契約の内容として具体的に定めずとも 、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護する よう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされていましたが、民法等の規定からは明らかになっていなかったところから、同条にて使用者は当然に安全配慮義務を負うことが規定されました。そして、この労働契約法上の保護を受けるには前述のとおり、労働基準法上の「労働者」に該当することが前提となっています。
このためか、前述の和田事件では、ファミリーマート(以下「FM」)側への責任を問う法的主張として、①FMが、亡被害者に対して負う安全配慮義務に違反したこと(民法709条)、②FMが、加盟店に対して、従業員が過労死基準を超えるような長時間労働があった場合にはこれを指導監督すべき義務を負っていたところ、当該義務に違反したこと(民法709条)、③被告加盟店の被害者に対する不法行為についての使用者責任(民法715条)を根拠として、不法行為による損害請求を行いました。 また、これらを裏付ける要件事実として「FMが加盟店の従業員の接客方法・態度等を教育・研修し、加盟店(オーナー)に対し、従業員の労務時間や給与等を報告させていたこと等」を指摘し、FMの強い支配性、「共同使用者性」若しくは「実質的使用者性」又は安全配慮義務を負う「特別な社会的接触関係」にあること等を主張しました。
この「特別な社会的接触関係」という概念は、事案は異なりますが、「テクノアシスト相模・大和製罐事件(東京地判平成20年2月13日労働判例955号13頁)」(注文者工場内において負傷、死亡した請負人会社元従業員の遺族が注文主・請負人(会社及び代表者)の双方に損害賠償を求めた事案<遺族勝訴>)において、「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものである」などで認められています。
和田事件では、判決前に和解が成立しており、原告側の主張に対する司法判断が示されることはなかったのですが、FMが今でいうレピュテーションリスク(reputation risk)を意識した結果の対応(和解の申出と和解金の支払い)であり、和解の申出をした理由の一つとして、FM側に加盟店から過労死基準を大きく上回っていた被災者の労働時間の報告が継続的になされていたことが判明したことが明らかにされています。当時、FMも報道機関の取材に対して、「今後も加盟店が労働法規を守るように指導していく。」とコメントしています。
本事案における親会社(本部)の責任
和田事件和解から約10年。今回の事案は依然して、FCコンビニにおける従業員はもちろん、加盟店主(オーナー)が過酷な労働環境に晒されている状況があることを物語っています。本事案において労災認定後における親会社(本部)と遺族の方に何か話し合い等があったかどうかは、報道もされていないのでわかりません。
仮に、遺族側が労災民訴を提起するとしたら(本部側の責任を問うなら)、前節記述のとおり、親会社(本部)の強い支配性、「共同使用者性」若しくは「実質的使用者性」又は安全配慮義務を負う「特別な社会的接触関係」にあること等を主張して、不法行為(共同不法行為)責任を問う方策もあるかもしれませんが、立証責任は原告側にあるのでそのハードルは決して低いとは言えないと思います。
FCコンビニ従業員の生命、身体の安全配慮の確保について
現行の労働基準法が施行されたのが、昭和29年です。この時代、「労働者」とは何ぞやと考えた時、その前提となる労働者と会社との雇用形態について、コンビニを含めた「FC契約」などのビジネスモデルは全く考慮されていなかったと思います(当然ですが)。
近年、FC契約を含めた多種多様なビジネスモデルの創出、ITの急速な発展により、リモートワークの普及が従来のオフィス勤務の概念を覆し、フリーランスやギグワークが一般化したことなど雇用形態にも大きな変化が生じてきていることは周知の事実だと思います。
現在、厚生労働省の労働政策審議会において、労基法上の「労働者」や事業、労使コミニュケーションのあり方、14日以上連続勤務禁止の法制化等について、議論が行われています。年内に議論をまとめる予定だそうですが、現在の多様なビジネスモデルや多様な働き方などを考慮し、本事案におけるFCコンビニ従業員が親会社(本部)との関係で労働基準法等の保護を受けられるよう、使用従属関係を類型化した特別法を制定し、当該従業員の「労働者性」を認める方向での労働基準法上の「労働者」の再定義を是非検討してもらいたいと考えています。
一方、労働基準法及びその他労働法規からのアプローチではなく、昨年11月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に係る法律」(いわゆる、フリーランス・事業者間取引適正化等法、以下「フリーランス法」)のように経済法からアプローチで、本事案のようなFCコンビニ又はその他のFC事業者の従業員の安全配慮義務を親会社(本部)に課す法律を制定する途もあるのではないでしょうか。
フリーランス法はいわゆる経済法のカテゴリーに入りますが、フリーランス(特定受託事業者)について、労働基準法による労働者保護の一部を切り出して、保護規定が設けられています(ただし、安全配慮義務については、特別に明記されていません。)。
実態として、親会社(本部)が、従業員の接客方法・態度等を教育・研修し、従業員の労務時間や給与等を報告させている実態やスーパーバイザーが訪店などで指導している事情等から親会社は加盟店主(オーナー)と一体的に加盟店を経営していることと同視することができ、そこに従事する従業員は加盟店主(オーナー)と雇用契約を結ぶことによりフランチャイズ契約という経済スキーム関係に組み込まれ、経営を一体的に行う親会社(本部)との関係において、擬制的にFC契約又は雇用契約を結んだとも解することもできることから、当該雇用契約の付随義務として信義則上、安全配慮義務を負うということを明文化すること方策もあるのではないでしょうか。
尤も、日本におけるフランチャイズビジネスの現状の箇所でも記したとおり、現在わが国の中では多種多様なFC契約によるビジネスモデルが展開されています。各業界毎に、経営方法、サービス内容、商品、営業時間、経営実態、親会社(本部等)との契約内容や役務の提供の内容などが違い、千差万別だと思います。故に、これらを一括りにして法制化することは、、中々ハードルが高い作業になるかと思います。
しかし、長時間労働・連続勤務による過重労働が顕著で、過酷な労働環境に晒されている実態が未だ改善されないコンビニエンスストアの従業員又は加盟店主(オーナー)に係る安全配慮義務規定の法制化については、優先順位が高い案件として、検討に値すべき懸案事項と考えます。
また、この問題の根本的原因は、24時間365日営業というコンビニエンスストアの経営方針があるわけです。便利な面、本事案のようなことも影で発生しています。親会社(本部)は、それを加盟店に課す以上、そのアフターケアーをしっかりしていくというのが、信義則上、求められるのではないでしょうか。さらには、24時間365日営業ということも見直す時期に来ているのではないでしょうか(尤も、コンビニは、震災など災害時おいて、「災害時帰宅支援ステーション」や「指定公共機関」として、帰宅困難者の支援や物資の供給など重要な役割も期待されているので、地域の特性、災害事情等を考慮して、柔軟な見直しを行うべきと考えます。)。
近年、人手不足が問題視され、人手不足を直因とした倒産も増加しています。外部環境が悪いだけに、コンビニの長時間労働、連続勤務による過重労働の問題はこれからもより一層、顕在化していく可能性があり、加盟店の廃業件数も増えていく可能性もあるかと思います。昨今は、Amazonを代表とするプラットフォーマーが、小売にとどまらない多様な事業を展開していますが、前記のように災害時における役割などリアルな店舗ゆえの有意性も期待されていることから(特に、災害発生が予見されている地方の地域では)、伏線として、私企業の観点より広い視野での工夫が求められるかと思います。
普段、私たちが当たり前のように使っている場所で、今回のような不幸な出来事が繰り返し起きています。そこで働く人たちの安全配慮の確保を図る法制化と業務運営の見直しについて、各方面又は業界全体で再検討すべきかと思います。
霖雨蒼生。