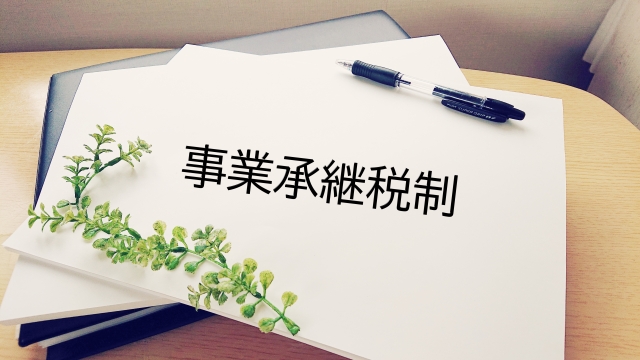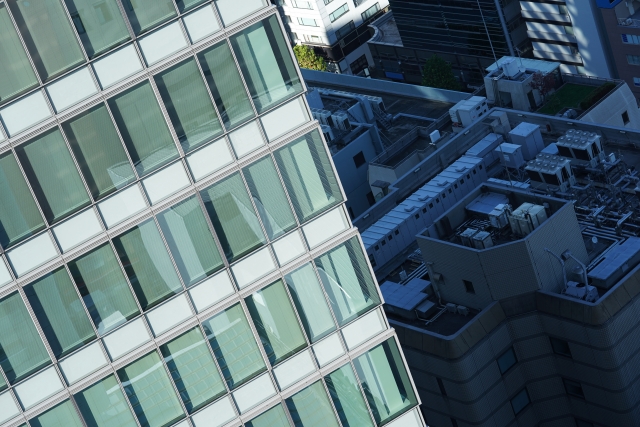今年2月5日、株式会社技術承継機構という会社が、東京証券取引所グロース市場に新規上場しました。
中小製造業のM&A(合併・買収)を手掛ける会社です。従来の投資ファンドと異なり、傘下の企業は他社に売却しないのが特徴。リスク分散で特定業種の取引先に偏らないような企業を傘下に治めてきており、平成30年(2018年)7月会社設立以来、上場までの間に、10社を譲受、1社と資本業務提携を行っています(同社ホームページより)。
技術を承継し、次世代に繋ぐ(中小製造業のグループ化)
同社のホームページ中に掲載されているミッションの中に「日本の中小を中心とする製造業は技術を持っているものの、後継者不足・営業不足等、『もったいない』状況にあり、その『もったいない』を改善したいという思いが会社設立の出発点です。」との記載があります。
日本の優れた製造技術が後継者不足等による廃業・解散等により消失していくことに対し、企業の譲受(M&A)及び譲受企業の経営支援に取り組んでいるのが、同社の特徴です。
従来の投資ファンドによる事業承継や再生型事業承継等では、経営陣にファンド関係を送り込み、投下資金の回収を行うため、被買収会社の株を売却する出口戦略(イグジット)を行うというのが、一般的でした。しかし、同社の場合、譲受した会社の再譲渡(売却)はせず、「長期的な目線で事業の継続と成長を目指します」(同社ホームページから)としています。
また、会社名やブランドを存続させ、雇用を維持し、譲受企業の望まないブランド変更や会社合併、リストラは行わないことを基本方針としています。
従来の支配するという感じではなく、優れた製造技術を持つ中小製造業のグループ化を図ることで、各社が持つ技術力が相乗効果を生み、また製品ライフサイクルの衰退期などの外部環境への変化にも対応できる体制となっています。
このように、中小製造業1社ではなし得ない技術力の発展や営業力の強化を大企業並みに展開できる環境を生成したと言えると思います。
この株式会社技術承継機構と同じように、M&Aによる中小製造業のグループ化を図り、成功している例として、由紀ホールディングス株式会社という会社があります。
同社は、精密切削加工業などを中心に、ニッチな分野で高い技術力を持ち、オリジナルの競争力の高い技術持つ中小製造業会社をグループ化し、経営資源(資金調達、事業戦略、人事採用、企画広報、技術開発など)のプラットホームをグループ会社に提供しているのが特徴で、この点は、株式会社技術承継機構と共通している部分があるかと思います。
また、同社では、グループ会社の優れた要素技術を応用し、製品のライフサイクルに合わせた事業展開も行っており、リスク分散にも対応しており、この点も株式会社技術承継機構との共通点とも言えます。
事業承継ファンドなど最近の金融支援など
最近の事業承継に関しての新たな金融支援等の動きについて、いくつかご紹介したいと思います。
新しい形のファンドの設立など
少し、情報が古くなりますが、今年の1月上旬の日本経新聞の朝刊に、みずほフィナンシャルグループによる中堅企業を対象としたMBO(Management Buyout)を支援する記事が掲載されていました。
総額100億円のファンドを立ち上げ、経営陣が創業者などの大株主から株式を取得する際に資金が足りないなどに一部を拠出する予定とのことです。当ファンドの立ち上げは、事業承継を躊躇する一つの要因になっている後継者の資金不足などの背景を踏まえたものとなっています。
このファンドは、拠出(=対象会社の株式を取得)する際に、主に議決権のない優先株式か劣後債を保有するスキームを想定、経営陣が大半の議決権行使を握れるようになっています。株式譲渡により、ファンドなどが経営権を握ることに抵抗感を持つ経営者もおり、このファンドでは、MBOにより経営権を握った後継者(経営陣)の経営の自由度が一定程度保てるというのが、大きな特徴になっていると思います。
また、事業承継のみが対象とはなっていませんが、本年1月27日に、ゆうちょ銀行と三井物産が中小企業などの成長を後押しすることなど目的に、共同で100億円規模のファンドを設立しています。具体的には、地方の中堅・中小企業などを中心に両社のグループが提携してPE(プライベートエクィティ)投資を行うものとなっています。三井物産の商社機能や情報網を活用して販売先や仕入れ先の開拓などを支援することになっています。
積極化する地域⾦融機関による事業承継⽀援
日本国内の中小M&Aの実施件数は増加しており、2022年度の実施件数は、事業承継・引継ぎ支援センターを通じたものが1,681件、民間M&A支援機関を通じたものが4,036件。計5,717件となっています(中小企業庁ホームページ「事業承継を知る」)。2014年度におけるM&A件数が362件なのに対し、8年間で約15倍強、5,355件増加しています。
このように、M&Aが広く認知され、利用されるようになってきていますが、近年、事業承継問題や経営資源の効率化を目的に、地域金融機関がM&Aを積極的に進めています。地方銀行、第二地方銀行、信用金庫など地域金融機関による専門投資会社の設立が相次いでおり、(株)レコフデータによると、2024年に実行した事業承継M&Aは922件あり、うち107件にファンドなどの投資会社が介在しているとのことです。10年前との比較では、ファンド経由のM&Aの案件は約10倍に膨らんでいるとのことです。
地域金融機関ファンドによる支援は一般的には、自行やグループ企業から人材を対象企業に送り込むハンズオンの支援が中心となるようですが、他企業から買収される場合と比較して、企業文化の維持や従業員の雇用維持が保たれる傾向にあるようです。また、地域に密着している金融金融機関ならではの地域性の理解、地域経済内のネットワーク網など地域基盤を活かした支援が可能になるのだと思います。
なお、金融支援ではありませんが、各自治体なども後継者難の地元企業の事業承継のために各種の取組みをしているようですが、石川県では、民間マッチングサイトを活用し、県内の後継ぎのいない会社について、最初から対象会社の会社名を明らかにする 「オープンネーム方式」で県内外から買い手を募るという事業を開始するということです(令和7年度予算措置)。
今後の事業承継の在り方のうち一つの案として
2024年度における中小等企業の倒産、休廃業・解散の状況
2024年度倒産の状況
帝国データバンクが本年4月8日に公表した「全国企業倒産集計 2024年度報」によりますと、2024年度の企業倒産件数は1万70件(前年度比+13.4%)となり、11年ぶりに1万件を超えたということです。中小零細規模(従業員数が10人未満など)の企業の倒産件数の増加が顕著になっているそうです(同日に公表された東京商工リサーチによる「全国企業倒産状況」においても、倒産件数は1万件を超え、そのうち、中小・零細企業の倒産件数について、同様の傾向があることが公表されています。)。
このような中、信用保証協会が肩代わりする代位弁済について、2024年では、件数及び金額が10年ぶりの高水準になったということです。この代位弁済を受けた企業の多くは零細企業であり、コロナ禍からの業績回復が遅れている状況と見られています。この代位弁済は、倒産の先行指標とされ、代位弁済を受けた企業はある意味倒産予備軍とも言えます。
また、ゼロゼロ融資を受けた企業が返済に窮し、元本返済を先送りできる「コロナ借換保証」(2023年1月に始まり、2024年6月末で終了)の返済が2026年9月にピークを迎えるということです。「コロナ借換保証」はある意味延命措置とも言え、利用した企業の多くが資金繰りが悪化しているのが常態化しているとのことです。
さらに、帝国バンクが本年1月20日に公表した資料(TDB Business View)によると、いわゆるゾンビ企業数(2024年11月時点)は推計22万8000社となり直近1年間で3万4000社減ったとされています(ゾンビ企業については、当ブログ記事「令和ルネサンス『コロナ緊急措置終了へ(中小企業支援のスタンスを経営改善・再生支援を軸とする方向に回帰、民間ゼロゼロ融資返済、本年4月が山場)、そして、この先(その2)』」をご参照)。
しかし、未だにゾンビ企業とされる約22万8000社のうち、17.2%にあたる推計3万9000社が「経常赤字」かつ「過剰債務」かつ「債務超過」に該当するとのことです。同資料ではこの企業について、「これら経営破綻の危機に瀕する企業(=倒産予備軍)」と表現しています。
以上のことは、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(いわゆる金融円滑法)下のリスケジュールの常態化やコロナ禍の手厚い金融支援が続いている間に、経営改革や事業回復に向けた抜本的な見直し等を行わず、過剰債務を抱えたまま事業収益回復が遅れ、資金繰りに悪化している中小・零細企業がまだ一定程度・多数存在するということです。
現在では、コロナ禍による政府の手厚い金融支援が終了し、政府の中小企業に係る金融支援が「資金繰り支援」から「事業再生」へと舵が切られています。さらに、外部・内部環境要因として、原材料・燃料高等、人件費の高騰、追加利上げ、価格転嫁、一部の業界では「2024年問題」、後継者難、乱高下する為替、直近では、米国による「相互関税」の発動(4/9に上乗せ部分について、90日間の猶予・停止措置がされましたが)など、経営コスト増に繋がる懸念材料や事業継続の障壁となっている課題が山積しています。このようなことを背景に、人手不足倒産、物価高倒産なども過去最多を更新しているとのことです(前記帝国データバンク「全国企業倒産集計 2024年度報」)。
休廃業・解散の状況(2024年)
帝国データバンクが本年1月20日に公表した「全国企業『休廃業・解散動向』調査(2024年)」によると、同年に休業・廃業、解散した企業は6万9019件に達したとしています。対前年比で16.8%、2016年調査開始以降から最多を更新したとのことです。同調査結果によると、休廃業する前の直前期の決算で当期純利益が「黒字」だった割合の企業は51.1%で過去最低を更新、このことから、同年の「休廃業・解散動向は総じて、直近の損益が悪化した企業が多い点が特徴」としています。
後継者難を原因とした倒産及び休廃業、解散の状況(2024年度・2024年)
前記の倒産状況及び休廃業、解散の状況のうち、後継者難関連をフォーカスすると、前記の「全国企業倒産集計 2024年度報」(帝国データバンク)によると、2024年度の「後継者難倒産」は507件(前年度586件、13.5%減)となっていますが、2年連続で500件超となっているとのことです。なお、「後継者難倒産」のうち、「経営者の病気、死亡」が約4割を占めているとのことで、この点は、注目すべき点だと思います。
また、休廃業、解散における後継者難関連としては、休廃業、解散時における経営者年齢は、2024年平均で71.3歳となり、前年から0.4歳上昇、調査開始以降で最高齢を更新したとのことです。最も休廃業が多い年齢も75歳と過去最高年齢となり、高齢経営者が体力的な面(限界)と昨今の事業を取り巻く厳しい環境を背景に、後継者に継がず、廃業しているケースが多いことが窺えられます。
今後の事業承継の在り方
2025年問題
事業承継の2025年問題と呼ばれる後継者不足の問題が以前より言われ、遂にその2025年に突入しています。2025年問題とは、いわゆる団塊の世代が2025年に75歳を超えることから、社会保障(後期高齢者医療保険など)をはじめとするさまざまな領域で生じるとされている問題のことです。
少し、古いデータになりますが、2019年中小企業白書によると、中小等企業経営者の平均引退年齢が75歳と言われていることから、2025年までに約245万者(社)人が引退することが見込まれ、その約半分の127万者(社)が後継者未定と言われていました。この約127万社が廃業した場合、約650万人の雇用が失われ、およそ22兆円ものGDPが消失すると試算されていました。
その後、後継者未定率は若干下がった(改善)のですが、依然として、大きな問題であり、その後の経済環境等の悪化(物価高、原材料・燃料高、人件費の高騰、円安など)などにより、それらの要因と二重、三重、四重、五重と重なり、倒産又は休廃業、解散に追い込まれている状況にあるかと思います。とりわけ、地方経済では、経営者の高齢化は都市部より顕著で、後継者難は地域経済にとって深刻な問題となっています。
また、最近では、「企業の自主的な廃業の増加に伴い、販路を失った取引先やサプライチェーンを担う事業者が連鎖的に事業継続を断念したケースも目立ってきた。」(前記帝国データバンク「全国企業『休廃業・解散動向』調査(2024年)」)という事象も生じているようです。
事業承継の着眼点、承継から継続へ
本記事冒頭にご紹介した、株式会社技術承継機構と由紀ホールディングス株式会社ですが、両社に共通するのが「優れた製造技術(要素技術)を持つ中小製造業のグループ化(経営資源の承継、連携)」を図るという点です。
着眼点は、経営者(会社)という箱物ではなく、その中身(=事業の価値)だということです。製造業でなくても、ブランド、特許など知的財産権、顧客、自社の優れた人材、営業のネットワークなど有意な経営資源があるかと思います。
また、前節の最後に記した”販路を失った取引先やサプライチェーンを担う事業者が連鎖的に事業継続を断念したケース”についても、その川上にある自主的に廃業した企業が廃業前に川下にある企業等に有用な事業だけを切り出して、事業譲渡や会社分割のスキームにより事業承継ができていれば、そのサプライチェーンにある企業の連鎖倒産等は避けられたかもしれません。
したがって、事業者単位(例:親から子へ)の事業承継という観点から、優れた経営資源(=事業価値)の事業承継(=事業継続)をこれから重要な着眼点とすべきだと思います。
この事を前提とすると、個々の企業は自社の強みと弱みを分析して、強みの磨き上げ、また、自力再建が困難な企業については、自社の持つ経営資源が優れたものである場合、それを残す(承継)していく途を考えるべきだと思います。
また、商圏、各地域において、事業がどのように繋がっているかのか(サプライチェーン)の把握、どのような優れた技術などを持っている企業があるのかを全体的に把握し、必要に応じ、事業承継M&Aのスキームをアレンジを担う存在も必要だと思います。そして、その役割は、既に記したように、その地域の特性をよく知る地域金融機関に期待するところです。最近では、地銀の再編等も検討されているようですが、隣接する地域特有の情報を共有し、より広い範囲での地域経済の活性化のため、先に例をあげた株式会社技術承継機構さんのような事業承継を取引先(融資先)を通じアレンジする機能を強化、また、融資先の事業の磨き上げを支援していく機能の強化がされていくことが期待されます(既に、似たような取組みはされているかとは思いますが)。
口で言うのは簡単で、中々難しいとは思いますが、当ブログ記事「労働政策審議会労働条件分科会「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」(仮称)の設置」でもご紹介した「企業価値担保権」(従来の不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図るため、有形資産(不動産や土地など)がなくても、企業の将来性が高ければ(将来のキャッシュフローなど)、成長資金を供給できるようなスキーム)が今後、実施・利用される予定となっています。
成長余力のある又は潜在力のある中小企業は、ローハンキングフルーツ(いわゆる伸びしろ)が高いと言われています。市場の衰退や製品のライフサイクル等により退場を余儀なくされる業種や企業が発生することはある意味、不可逆的なことではあり、致し方無いと思いますが、成長力等の高い企業又は事業を活かすことにより、市場から退場した企業の従業員等を吸収するポテンシャルが生まれれば、その地域の活性化は持続的なものになるかと思います。
如何に、原石(成長性等のある事業)を見つけることができるか、また、原石(同)を見つける目利きの利いた人材を育成するか、そしてそれをどのようにアレンジしていくかの調整能力を、地域金融機関に期待するところです。